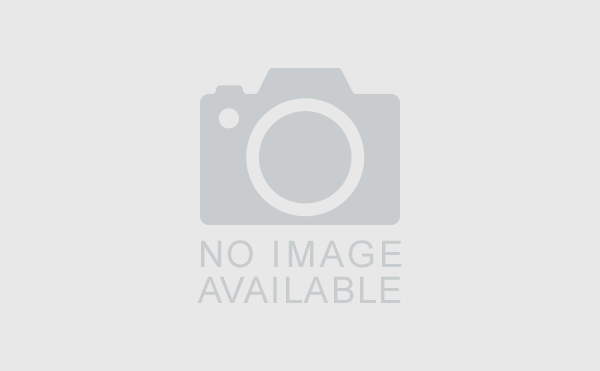やさしい経済学「中国の不動産市場」中岡深雪北九大教授
中岡深雪北九大教授が、日本経済新聞電子版で、やさしい経済学「中国の不動産市場」を寄稿しています。
2024年8月6日から2024年8月14日までの7本の記事の概要は、下記の通りです。
---------------------
不動産市場の不振が中国経済の足かせになっている。しかし、それは新型コロナウイルス感染拡大後のことです。それまで不動産市場は住宅開発を中心に、20年以上にわたって成長を続けた。
2023年までの20年間の中国の不動産投資額は155兆9879億元(約3400兆円)で、同期間の国内総生産(GDP)累計額の12%を占めます。不動産投資の約7割は住宅投資です。豊かになる過程で、人々の住環境改善への欲求が高まり、住宅ブームが起こった。
住宅制度改革の最初の取り組みは「私有化」です。それは、都市部の人々が籍を置く「単位」からの払い下げという形で進められた。単位が従業員に対し、所有権を格安で分譲し始めたのです。
ただ、従業員全員に払い下げることはできません。勤続年数や職歴などで優先順位を決めたため、1980年代から90年代にかけて実施された払い下げは、結果的に年齢の高い人が対象となりました。当初は払い下げを受けられても、住宅の転売は認められず、所有権の売買が認められたのは、99年の改革からです。
需給によって価格が決まる住宅の「市場化」により、都市間格差がはっきりしてきた。
一線都市は不動の北京、上海、広州、深圳で、住宅価格は圧倒的に高く、価格上昇も長らく高い水準にあった。
中国の憲法は土地について、都市部では所有権は国家に属し、農村部は原則として集団所有に属する、と定めています。土地譲渡収入(使用権売却の金額)は地方政府に納められる。地方政府にとって重要な資金源となっている。
改革開放以降、住宅供給体制の見直しが行われ、自由に住宅を購入できるようになった。
中国政府は1998年に「都市部住宅制度改革を一層深化させ住宅建設を加速させることに関する通知」を出し、住宅の「実物分配」を停止し、金銭面で補助する「貨幣分配」という概念を提起した。
習近平は2016年12月、経済の運営方針を決める中央経済工作会議で「住宅は住むもので投機の対象ではない」とした。
目的は、投機熱を冷まして不動産不況が訪れた際のダメージを緩和することと、住宅を保有しているかどうかが国民間の資産格差につながっているので、その格差を緩和しようとした。
中国の不動産開発企業の売上高ランキングは、大きな入れ替わりが少なく、大手が開発する住宅(マンション)は、安定した人気を維持してきました。
しかし2022年以降、状況は変わり、大手の恒大集団、碧桂園、万科企業などが、デフォルトや経営不振になり、どの企業が安泰なのか不明になってきている。
不動産開発企業が次々に不振に陥った原因は何でしょうか。「ゼロコロナ政策」で中国経済が縮小した影響もありますが、投資の過熱を抑制するために導入した「3つのレッドライン」や総量規制の政策的影響も無視できません。
---------------------
やさしい経済学「中国の不動産市場」[日本経済新聞電子版会員限定記事]
https://www.nikkei.com/topics/17092100
中岡深雪北九大教授のプロフィール
1998 大阪市立大学卒
2001 中国復旦大学経済学院高級進修生
2008 U.C.Berkeley Center for Chinese Studies Visiting Scholar
2023 北九州市立大学教授
専門 中国経済論、アジア経済論
https://www.kitakyu-u.ac.jp/env/about/introduction/basis/miyuki-nakaoka.html